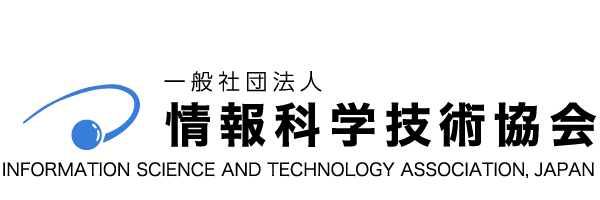活動方針
1)巨大化を避け、適性規模を保っている。
2)世話役はいるが強力なリーダーはいない。
3)常に全員が何かを創造しており、作る者と享受する者とが分かれていない。
4)金銭がかからない。
5)他の人間や他のグループに開かれ、出入りが自由である。
6)存在を目的とせず、一回限りの場合もある。
7)他のメンバーに関わり過ぎず、無関心にもならない。
8)様々な年齢、性、階層、職業が混じっている。
9)外の情報を把握する努力をしている。
10)「連」を構成する目的はとりあえず具体的で明白であるが、それをはみ出す場合もある。
メンバー紹介
桐山 勉(コアパーソン)、 川島 順、 栗原健一、 藤城 享
2025年度活動計画
1.特許情報検索・解析のための支援システムの動向検討
2.情報専門ジャーナルのトピックス記事紹介(数回/年)
3.日米欧の知財関連ユーザー会活動情報の収集・分析と海外連携
4.外部知財活動に対する支援・連携の活動と委員派遣(講演を含む)
5.Webツール活用による部会活動の効率化
6.情報交換:メンバー各自による自由プレゼンテーション
7.当部会HomePageからの有用情報の発信とメンバー募集
8.オンラインVR活動方式の研究。ZOOM方式
活動経過
2025年06月
1.今年の研究テーマ。「CO2を原料として利活用して有用な製品を作る技術」に関する
(全員での自由討議と進捗報告)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探し、分析する。
・JapioYEARBOOK2025の第4-3C原稿案を6/2に事前に見て貰い、
ポイント数とWORD承認済にしてもらい、白黒で見やすくなった。
・チェック後の第4-3C原稿案を6/2の夕方に他のPDG部会メンバーに
事前配布して、6/4の臨時PDG部会までに事前にチェックして貰った。
・6/4の当日に、PCが変わったために、ZOOMがPCで立ち上げられず、
急遽、Teamsの招待状を発行して貰い、30分遅れで臨時PDG部会を実施。
・誤字脱字、修正箇所を教示して貰った。更に、第9章と
第10章の内容について、自由討議した。
・特に、別途に開催されたセミナー(LexisNexis-PatentSight)の報告をされ、
第9章の中味について修正ポイントが明確になった。つまり、「生成AIの活用は
本人が色々な処で各種AIの情報と知識を把握した後で、本人自身が活用試行してから
実践活用のコツ(秘訣)を本人自身が把握しないと意味がない」と、判明した。
・以上の結果を踏まえて、6/18の7月度定例PDG部会までに第5原稿案を作成する。
2.トピックス話題提供:時間なく、特になし。
2025年05月
1.今年の研究テーマを固定。「CO2を原料として利活用して有用な製品を作る技術」に関する
(全員での自由討議と進捗報告)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探し、分析する。
・GXTI分類の詳細検討結果を事前に頂き、その詳細説明を約30分で受けた。
・JapioYEARBOOK2025の第3稿案と掲載したい図を事前配布。
・JapioYEARBOOK2025の第3稿案の20個の図の案―PDFを40分以上かけて説明し、
その後で質疑応答を行った。
・Japio指定のWordテンプレートを使用せず、一般のWord(図と本文)と、
Notepadの本文文章だけを速読流し読みして、全体を説明。
・その後で、全員で自由討議を行った。6月4日に臨時PDG部会を開催することを再確認。
・Japio指定Wordテンプレートを使用して、事前の6月2日までに
第4原稿案をPDG部会の全員に資料を事前送付する。
2.トピックス話題提供:時間なく、特になし。
2025年04月
1.今年の研究テーマを固定。「CO2を原料として利活用して有用な製品を作る技術」に関する
(全員での自由討議と進捗報告)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探し、分析する。
・JapioYEARBOOK2025の第2稿案を事前配布と当日、読み上げ。
JapioYEARBOOK2025の第2稿案の約10個の図の案―PDFを約1時間以上かけて説明し、
その後で質疑応答を行った。
・ストーリーと特許調査する8領域を決めた。その後で、約10個の図案に書いた特許群に対して、
GXTT分類を調べて貰うことを依頼した。
・ゲストとして担当理事に参加者して頂いた。最後に感想を頂いた。
・「CO2を原料として利活用する技術に関する特許分析」のJapioYEARBOOK2025の
第3稿案を次回のPDG部会に公表する。
6月30日の締切日までに、第5稿まで、その都度、Version-Upさせる。
・5月7日の臨時PDG部会を中止し、6月4日に臨時PDG部会を設ける。
2.トピックス話題提供:時間なく、特になし。
2025年03月
1.今年の新規研究テーマを固定した。(全員での自由討議と進捗報告)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探し、分析する。
・新規研究テーマ「CO2を原料として利活用して有用な製品を作る技術」に関する
特許の味見検索の結果をGXTT分類で比較詳細検討結果
ゲスト参加者として、多大な貢献をPDG部会は受けた。(絶大な協力者)
・CO2を原料として利活用する技術に関するJapioYEARBOOK2025原稿案(完成度20%)
自由討議:ゲスト参加者から「図1と図2に関して、令和に入社した現役の
若者向けの資料になっていない。「特許情報の哲学者」かもしれない。昭和の現役
には、少しは参考にはなるかもしれないが、令和と平成の現役には全く参考にならない」と
コメントとアドバイスを得た。⇒大幅に図1案と図2案を改善する必要がある。
・Word集約表に関する自由討議:「CO2⇒C1化学、C2化学、C3化学などは
一般素人には理解しにくい。CO2⇒新航空ジェット燃料、船舶用新燃料、
陸上輸送車両用新液体燃料、タイヤなどの市民に理解しやすい分類に変えた方が良い」
・今回、JapioYEARBOOK原稿案叩き台素案をPDG部会に内部公開して良かった。
・Windows11上で動くOffice365-2024年版ではCopilotが1日300件まで無料で使える。
ここに焦点をあてた「マニュアル型の図」に抜本的に改訂するのが良いと判明した。
2.トピックス話題提供:時間なく、中止。
2025年02月
1.今年の新規研究テーマを固定した。(全員での自由討議と進捗報告)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探し、分析する。
・新規研究テーマ「CO2を原料として利活用して有用な製品を作る技術」に関する
特許の味見検索の結果報告(PPTX、進捗報告)を提供
・CO2を原料として利活用し、中間体を経由してエチレン、プロピレン、ブタジエンを作り、
最終的にはポリカーボネート、ポリエステル、タイヤなどを製造する技術の特許分析。
・CO2⇒SAF航空燃料の特許群をTHE調査力にて評価し、評価Aの特許リストから、
GXTIのどの分類に多く含まれるのか特許分析を依頼。
・CO24⇒SAF航空燃料(Shatrresearch検索)の評価Aの特許群と
CO24⇒SAF航空燃料(JDreamⅢ検索)の評価Aの特許群との2種類の正解候補
小母集団によりGXTI分類による詳細解析結果を解説してもらった。
・今回の詳細GXTI分類分析を他の正解小母集団候補の特許群に対しても
同様に詳細特許分析をすることになった。
(正解候補小母集団をGXTI分類による詳細解析を他分野にも拡張する。)
・Windows11上で動くOffice365-2024年版ではCopilotが1日300件まで無料で使える
ことが判明した。
2.トピックス話題提供:時間なく、中止。
2025年01月
1.今年の新規研究テーマを固定した。(全員での自由討議と進捗報告)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探し、分析する。
・新規研究テーマ「CO2を原料として利活用して有用な製品を作る技術」に関する
特許の味見検索の結果報告(PPTX、進捗報告)を提供
・CO2を原料として利活用し、中間体を経由してエチレン、プロピレン、ブタジエンを作り、
最終的にはポリカーボネート、ポリエステル、タイヤなどを製造する技術の特許分析。
・生成AI-Microsoft-Copilotで、依頼の約29中分類に関して、進捗状況の報告。
Copilotは、特許と文献(Web及び学術文献)の両方の回答が出力される。
・お互いにデータの共有化の為に、関係特許番号表を、THE調査力AIに蓄積した。
・中分類に相当するGXTIの分類が対応しているか、チェックする事に決まった。
・2025年度のINFOPROシンポジウムは、12/4-12/5と判明した。
更に、JDreamⅢが利用できる様になり、各ヒット解答に類似特許20件と
類似JDream検索が可能になった。画期的。
2.トピックス話題提供:時間なく、中止。
2024年12月
1.今年の新規研究テーマを固定した。(全員での自由討議と進捗報告)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探し、分析する。
・新規研究テーマ「CO2を原料として利活用して有用な製品を作る技術」に関する
特許の味見検索の結果報告(PPTX、進捗報告)
・CO2を原料として利活用し、中間体を経由してエチレン、プロピレン、ブタジエンを作り、
最終的にはポリカーボネート、ポリエステル、タイヤなどを製造する技術の特許分析。
・生成AI-Microsoft-Copilot有料版を正式に利用しているとの報告。
味見検索などの予備処理をできるだけスピーディに短時間でこなす事が会社では必要。
日経新聞情報とWeb情報から手間暇を掛けて帰納法的に予備処理をしているが
もはや、一般の大手企業では「その様なスロー型予備調査は許されない」との事。
約29項目の小分類の全件に対して、Microsoft-Copilot調査の応援を依頼。
・Gサーチ社から特別にJDreamⅢをPDG部会の研究用に利用することが許された。
学術文献の検索ヒット結果の各解答の右側にLINK機能があり、
更に、各ヒット解答に類似特許20件と類似JDream検索が可能になった。画期的。
・約29項目の小分類の特許集約は12/11までには完成しなかった。
次回の2025年1月22日のPDG部会まで、特許集約を延期した。
・出願人検索でヒットが無かった企業特許を調べる。
2.トピックス話題提供:時間なく、中止。
2024年11月
1.今年の新規研究テーマの候補を固定した。(全員での自由討議)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探す。
・新規研究テーマ候補「CO2を原料として利活用して有用な製品を作る技術」に関する
特許の味見検索の結果報告(PPTX)
・CO2を原料として利活用し、中間体を経由してエチレン、プロピレン、ブタジエンを作り、
最終的にはポリカーボネート、ポリエステル、タイヤなどを製造する技術の特許分析。
・上記テーマに関する特許分類(IPC,FI,Fタ―ム)の資料提供と説明があった。
・生成AI-Microsoft-Copilotによる「CO2からパラキシレンを作る技術」の
検索した結果の紹介があった。
A)NEDOプロジェクトのWeb情報:国立大学法人富山大学、千代田化工建設、
日鉄エンジニアリング、日本製鉄、ハイケム、三菱商事は共同で
NEDOの「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/CO2排出削減・
有効利用実用化技術開発/化学品のCO2利用技術開発」:
B) 富山大学と千代田化工建設、日本製鉄と共同してCO2からパラキシレンを作る。
C) 新しいC1化学反応の創成:二酸化炭素からパラキシレンを直接合成するための
新規ハイブリッド触媒の研究(J-Stage掲載の論文)
・次回12/11のPDGまでにできるだけ「CO2利活用技術」を生成AIと特許検索検索の
両方から真剣に集中して仮母集団を構築する。
・資料の出願人検索でヒットが無かった企業の特許を調べる。
2024年10月
1.今年の新規研究テーマの候補案を考える。(全員での自由討議)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探す。
・新規研究テーマ候補案の4案に関する特許の味見検索の結果報告
・CO2を原料として利活用し、中間体を経由してエチレン、プロピレン、ブタジエンを作り、
最終的にはポリカーボネート、ポリエステル、タイヤなどを製造する技術の特許分析。
・新加入メンバー3人が増えた。2023年に検討した過去の資料の紹介があった。
・新メンバーの利用できる特許検索システムの紹介
・新メンバーは、現役の人達であり、プロフェッショナルの意見を貰い、刺激を貰った。
自由討議が具体的な過去の集約資料を提示しながら説明され、PDG部会のレベルが
一気に、現役者のプロレベルに上がった。
・ZOOM会議の録画を観て、Chatの中に提示された資料がダウンロード処理の間に
電子的に壊れたが、Webを調べまくり、大方の集約資料を入手した。
・①CPC分類のY02分類の詳細と、特許庁資料GXTIプロジェクトを学習。
・11月中に、JapioをPDG部会が訪問し、面談を申し込む予定。
2.PDG部会のメンバー増加には、一応、成功した。当面はこの8人態勢で研究したい。
3.トピックス話題の提供:
・上記の1)項で時間を十分に使い、他の事を話す時間は、残らなかった。
2024年09月
1.今後の新規研究テーマの候補案を考える。(全員での自由討議)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探す。
・今後の新規研究テーマ候補案の4案に関する特許の味見検索の結果報告
・先月8/21のPDG部会ででた案件に関する具体的な特許の味見調査。
例えば、
・メタン、メタノール生成技術によるCO2の再利用。
S10082-239件より絞込し、49件に栞印をつけ、THE調査力AIの
MENU-828及びMENU-829に電子データを蓄積。代表特許抽出。
・CO2を原料としてプラスチック製造技術の味見検索。
S10038-5件、パラキシレン製造→MENU-832に蓄積し、代表特許抽出。
S10035-382件、各種樹脂製造→MENU-833に蓄積し、代表特許抽出。
・水素と反応させたCO2の燃料変換技術 (途中)
・CO2利活用技術の過去の各種調査結果のURLを調べる。
2.PDG部会のメンバー増加を真剣に考える。
・今年一杯、各自の知人に1本釣り方式にて当たってみる。トライアル参加を誘ってみる。
3.トピックス話題の提供:
・健康長寿のABC:帝人大阪高槻繊維研究所のOB会9/17の講演話題を提供
2024年08月
1.今後の新規研究テーマの候補案を考える。(全員での自由討議)。
・市民科学者として、SDGs関連テーマの課題を特許情報から探す。
・今後の新規研究テーマ候補案30件をGoogle Gemini 1.5Proに提案して貰った。
・本日8/21の自由討議では各自に1個づつ選択抽出してもらった。
例えば、
・メタン生成技術によるCO2の再利用
・メタノール生成技術によるCO2の再利用
・水素と反応させたCO2の燃料変換技術 などを、とりあえず、仮候補として、
10月のPDG部会まで、「今後の新規研究テーマ」を継続して探すことにした。
2.PDG部会のメンバー増加を真剣に考える。
・今年一杯、各自の知人にトライアル参加を誘ってみる。
3.トピックス話題の提供:
・「IKIGAIとは」「Happier lifeとは」「幸わせとは」に関して、各自の意見を交換。
小さい目標を持つ。経済的に困らない。などの意見がでた。
2024年07月
1.今年の新規研究テーマ『代替食と未来の食品供給に関する特許分析』の発表結果の反省。
・7/5の午後に発表したプレゼンの発表報告。
発表後に会場にて、質問があった。
発表12分+1件の質疑応答3分で、ちょうど15分になって、終了。
会場で100名弱+オンラインで150名以上の参加者があった。
・オンラインで参加した感想。
・会場でリアルで聴かれた担当理事の感想。
・INFOPROシンポジウムの発表を対外発表(その1)と位置づけ、同時並行にて
JapioYEARBOOK2024に対外発表(その2)と位置づけて、投稿した。
・INFOPROシンポジウムの発表は概略、盛会に終わり、成功したと判断した。
2.トピックス話題の提供:
INFOPROシンポジウムの反省会で時間を全て使い、
トピックス話題を話す時間的余裕がなかった。
2024年06月
1.今年の新規研究テーマ『代替食と未来の食品供給に関する特許分』の発表練習。
・PDG部会の本テーマとして研究を2023年12月以降から実施中。
・INFOPROシンポジウム事務局に発表資料を6/30に提出するために、事前配布。(5/17夜)
事前にPDG部会メンバーに配布した。
・発表プレゼン案を13分以内で説明するために、Note文を作成した。
・PDG部会で13分以内で、リハ―サルを実施。(ZOOM-オンライン説明)
・全員で、プレゼンを聞いた後で、自由討議を1間以上掛けて実施。
・想定Q&Aの具体例。(6件ぐらい実施。7/3時点で想定Q&A10問を準備。
全員で、その他の想定質問をあげて、自由討議を実施。
・INFOPROシンポジウムの事務局に、最終PPTXを6/30午後に提出済。
・平行作業として、JapioYEARBOOKの執筆原稿(完成度80点)を6/30午後に、
JapioYEARBOOKの事務局に提出すみ。
2.トピックス話題の提供:
INFOPROシンポジウムの準備の自由討議で時間を全て使い、
トピックス話題を話す時間的余裕がなかった。
2024年05月
1.今年の新規研究テーマ『代替食と未来の食品供給に関する特許分』各自検討の報告。
・PDG部会の本テーマとして研究を2023年12月以降から実施中。
・INFOPROシンポジウム事務局から「査読結果」の連絡。(5/24、11時頃)
査読結果がPDG部会の当日までに届かなかったので、発表プレゼンの討議に専念。
・発表プレゼン素案を事前に配布し、当日、約15分でプレゼンリハーサル実施。
・9つのカテゴリー特許事例がこれで良いのか、見直しを実施。
・全員で、プレゼンを聞いた後で、自由討議を1間以上掛けて実施。
大変、参考になった。ZOOM会議をレコーディングしておいて後で聞き直し実施。
・想定Q&Aの具体例。(2問のみ。ピックアップ)
全員で、その他の想定質問をあげて、自由討議を実施。
・PDG部会の以後に、事務局から査読結果を頂き、桐山の修正案を5/28の9時前に配布。
今年度の1段組テンプレートに修正。特許検索の説明を追加。
挿入図の8個の見直し。図2の特許分類解析事例の図を新規に作成し、追加挿入。
査読者のご指摘事項に沿って、全面的に修正。
2.トピックス話題の提供:
INFOPROシンポジウムの準備の自由討議で時間を全て使い、
トピックス話題を話す時間的余裕がなかった。
2024年04月
1.今年の新規研究テーマ『代替食と未来の食品供給に関する特許分』各自検討の報告。
・PDG部会の本テーマとして研究を12月以降から実施中。
・INFOPROシンポジウム事務局から「発表の採用合格」の連絡。(4/17、16時過ぎ)
・A4-4頁の予稿集原案を事前配布(4/16朝9時前)し、PDG部会の当日に
1時間の時間を取り、全員で自由討議した。
・メモ(A4-4頁の予稿案に対して)で、「言いたいことは何か」をメンバーに聞き、
メンバー全員の自由討議を実施しできた。。
・発表資料PPTX原案から「発表資料に入れるべき頁」の24枚のスライドを選んだ。
・INFOPROシンポジウム事務局には、予稿集A4-4頁を5/7までに提出する際に、
「発表時間20分(発表15分+Q&A-5分)の希望」を添えて提出すことにしたい。
2.トピックス話題の提供:
INFOPROシンポジウムの準備の自由討議で時間を全て使い、
トピックス話題を話す時間的余裕がなかった。
・米国PIUG総会の聴講だけの参加を検討したが、あまりにも参加費(5万円以上)が
高く、Web参加の申し込みを断念した。
2024年03月
1.今年の新規研究テーマ『代替食と未来の食品供給に関する特許分』各自検討の報告。
・PDG部会の本テーマとして研究を12月以降から。
・「代替食の分類事例(TREE図)」の紹介があり、大変 参考になった。
調べれば調べる程、代替食の分類化は難しく、PDG部会の羅列方式の独自分類で
INFOPROシンポジウム発表する全員合意を得た。
・今年のINFOPROシンポジウムでは予稿集の制限既約がA4-2頁になった。
ちなみに、2頁の予稿集案を作成したが、内容を殆ど掲載できない事が判明した。
・参考までに、発表用のPPTXの叩き台素案を作成して、発表時間が20分
(発表15分+Q&A5分)を希望することを、申込書の備考欄に記載することにした。
・一応、7/4または7/5の一般口頭発表の具体的な内容イメージがPDG部会で共有化でした。
・INFOPROシンポジウムの一般口頭発表を申込を3/29に行う。
2.トピックス話題の提供:
INFOPROシンポジウムの準備の自由討議で時間を全て使い、
トピックス話題を話す時間的余裕がなかった。
2024年02月
1.今年の新規研究テーマ『代用食と未来の食品供給に関する特許分』各自検討の報告。
・PDG部会の本テーマとして研究を12月以降で始めた。
・「代用食の纏め」Wordファイルを再吟味した。
・一般口頭発表のエントリー準備の素案の概要を示した。(WORD1頁)。
7個のカテゴリー分類の仕方を上位下位も含めて、TREE構造に再検討することで合意。)
・9個のカテゴリーの代表的な特許事例素案を紹介。
・予稿集の提出締切日が5月上旬に決まったので、次回の3月度部会にて、
最終のエントリー申込書を決め、4月度のPDG部会にて予稿集(案)を決める。
(両方とも、PDG部会メンバー間のメール交換で検討する。)
2.INFOPRO2022シンポジウムで発表した内容の特許出願のフォロー。
・知財権を持っているJP7199585B2と3年分の実施権と、PCT公開の
WO2023/218750A1の権利を無償で企業Aに移譲(遺贈寄付)することに、発明者全員の合意を得た。
3.トピックス話題の提供:
・INFOSTA-SIG担当理事に、2024年度の作業報告書を提出した。
2024年01月
1.今年の新規研究テーマ『「食物ロス」&「代用食」の特許分析研究』各自検討の報告
・PDG部会の本テーマとして研究を12月以降で始めた。
・「代用食の纏め」Wordファイルの再説明の後で、
先生も含めて、全員で「代用食」に的を絞り、INFOPROシンポジウムに
エントリーする方向に、PDG部会合意がえられた。
・一般口頭発表のエントリー準備を行う。また、その予稿集(WORD4頁、または6頁)の
準備に取り掛かる。
・引き続き、各自で検討を継続することで、合意した。
2.INFOPRO2023シンポジウムで発表した内容の特許出願のGive-Up。
・総トン数500t以上の鉄製の船舶の錨とアンカーチェインは鉄製に限るという国土交通省の
法規があるので、非鉄製のアンカーチェインの特許出願はGive-Upする。
3.トピックス話題の提供:
・1/19に開催された「INFOSTA新春セミナー」の報告
2023年12月
1.今年の新規研究テーマ『「食物ロス」&「代用食」の特許分析研究』各自検討の報告
・12月のPDG部会までは仮テーマで検討して来たが、1月より本テーマとする。合意。
・「食物ロス&代用食の纏め」PPTX資料、改訂版の説明。
・「代用食と未来の食品供給」総合分析を、ChatGPTを活用して検討。
その資料の説明に基づいて、詳細に討議した。本テーマを「代用食」に絞ることに
関して3人は仮賛成した。先生が欠席なので、本決めは1月度まで延期する。
・「食品ロス」に関しての「纒め総括的な資料」が提示された。
・毎月、提言版のUpgradeの進捗報告をすることにした。
・引き続き、各自で検討を継続することで、合意した。
2.INFOPRO2023シンポジウムで発表した内容の特許出願の検討。
・図面のWordファイル化の進捗状況を報告した。
3.トピックス話題の提供:
・11/24に開催された「ChatGPTの活用法(第2段セミナー)」の報告
2023年11月
1.今年の新規研究テーマ『「食物ロス」&「代用食」の特許分析研究』各自検討の報告
・10月に引き続き、ビヨンドミー社の基本特許等の紹介と、PPTX資料の
追加分とVersion-Up資料の報告。
・「宇宙食、繭、蚕の特許調査」。NASAを中心に米国でも研究がされている。
世界で最も研究が進んでいるのは、中国の月面エコロジーの研究の繭食の研究である。
・「10月に引き続き、「食物ロス&代用食」の提言のUpgrade版を示し、
今後とも毎月、提言版のUpgradeの進捗報告をすることにした。
・引き続き、各自で検討を継続することで、合意した。
2.INFOPRO2023シンポジウムで発表した内容の特許出願の検討。
・疑似錨の重さを200kgから300kgにする軽量版疑似錘の複数個を取り付ける案を示した。
3.トピックス話題の提供:
・INFOSTAセミナー「ChatGPTの活用法」を受講して、「食物ロス」「代用食」の
具体的な利用法の事例紹介があった。
11/24にはChatGPTの活用法(第2段セミナー)があるとの連絡。
2023年10月
1.今年の新規研究テーマ『「食物ロス」&「代用食」の特許分析研究』各自検討の報告
・10月に引き続き、ビヨンドミー社の基本特許等の紹介と、PPTX資料の
追加分とVersion-Up資料の報告。
・「食品ロス検討資料」LINK集約資料の大作を報告。
「食品ロスとフードロスの違いについて」質問がでて、解答表示。
・「10月に引き続き、「食物ロス&代用食」のドライ食品を追加したVersion-Up
資料と、関連Fタームの集約表を紹介。
・引き続き、各自で検討を継続することで、合意した。
観点からBoothを回って、10社の簡易報告をWordファリルで報告。
2.INFOPRO2023シンポジウムで発表した内容の特許出願の検討。
・特許法の新規性喪失の例外規定を活用するのなら特許出願しか、方法がないと判明。
改めて、桐山が頑張って努力して明細書案を作り、先生に明細書を作成・出願を
お願いする。
3.トピックス話題の提供:
・JR東海名古屋駅周辺の地域熱供給プラントの見学報告。
一般には非公開の地下にある地域熱供給パイプラインネットワークの見学報告。
現在、東京、大阪、名古屋の大都市の再開発で行われいるCO2排出削減の具体事例。
2023年09月
1.特許情報フェア&コンファレンス(9/13~9/15開催、東京ビッグサイト)の参加報告
・15個のBoothを訪問し、そのプロバイダーから得た情報と感想の報告。
EXCELシートにて報告。AIとChatGPTに関しても報告され、非常に役立った。
・「ChatGPTを各社がどのように取り組み、応用しようとして居るのか」と言う
観点からBoothを回って、10社の簡易報告をWordファリルで報告。
2.今年の新規研究テーマ『「食物ロス」&「代用食」の特許分析研究』
・「秩父161(食物ロス)」「秩父162(代用食)」を提供頂いている。
その内容の関連特許の調査を8月度PDG部会に引き続き、行った。
・関連特許をPPTX資料とEXCELファイルに纏めて、報告提供。
8月度に続き、大変参考になった資料の提供であり、PDG部会で共有化ができた。
3.JapioYERBOOK2023に執筆した記事の内容に関する特許出願の試み。
・「30トンの本錨を6000mの深海海域に高強度長繊維の極太係留ロープを用いて
錨泊させる際に、本錨帆から10mから50mの離れた位置に縦割り擬似錨を
バネ付きボルトナットを用いて緊張下で脱着可能なことを特長とする係留方法」の
趣旨の特許出願の叩き台素案をもって、仮承認を得た。全員が賛成。
4.トピックス話題の提供: 省略。
2023年08月
1.INFOPRO2023シンポジウムにて発表した錨泊方法の特許出願 (自由討議)
・30トンの主錨の把駐力を最大化するために、疑似錨、または重りを設けるアイデァを
PPTX資料を用いて、説明。
・実用新案S56-146696,海洋構造物の係留方法の第4図の(C)図に
重りを付ける図があり、公知であるとの、意見がでた。(C)図は、従来法の事例として
実用新案に明記してある。
・縦割り重りの形状と取り付け・脱着の仕方に特徴を持たせて、進歩性を
出せないか、工夫してみたらどうか。また、締め付ける際にアンカーロープを
痛めないように、Rを取ったらどうか。
・実用新案であればモノになり、方法考案は実用新案にできない。
・30トンの主錨の水平方向の把駐力を最大化するために主錨の水平角度を0度にするために、
縦割型取り付け・脱着可能な重りに何らかの進歩性を持たせるように請求項を文章化して、
係留方法または係留システムとして、特許出願する方向で検討したらどうか。
・川島先生が納得される請求項の文章案の作成。
・本件の特許出願に関する自由討議で、時間を使いつくした。
2.今年の新規研究テーマとしての「食物ロス」「代用食」に関して。
時間を取れずに、遺伝子組み換え食品(GMO)に関しては、後でメール交換にて
連絡しあうことにした。(カルタヘナ議定書に関して、メール。8/24夜)。
2023年07月
1.INFOPRO2023シンポジウムの発表を聴いて (感想の意見交換)
・桐山の発表と、一般発表で実際に聴かれた発表と、Talk & Talkと特別講演の各自の感想について、
意見交換を行った。
・特許法30条-第2項の「新規性喪失の例外規定」の説明があり、
7/6に発表した内容で1年間未満であれば、特許出願が可能との説明があった。
2.INFOPROシンポジウムで発表した内容での特許出願に関して(全員で自由討議)
・単に6000mの海底で30トンのアンカーロープで固定し、錨泊する請求項では
「スカート サクション方式」の海底固定の文献があり、特許化できない。
・洋上風雨力発電のスカート・サクション方式の海底固定のことしか、知らない。
大林組の特許がある筈。(特許06264776、特開2015-034430を7/20の夜にPDG部会メンバーに連絡した。)
・2-3カ月以内に、代替クレーム案を作成する。
3.来年のINFOPROシンポジウムに向けての、今年の研究テーマ案の自由討議。
SDGsに関連するテーマとして、「資源ロス(1)、食物ロス」と
「資源ロス(2)、代用食」の提案があり、資料として「秩父161号」と「秩父162号」が
提供された。7月のPDG部会からその味見特許の紹介があった。
2023年06月
1.INFOPRO2023シンポジウムの発表準備 (リハーサル、Q&A練習)
・一般口頭発表の発表順序が「A3で7/6の11:30から30分と決まった。
・準備したINFOPRO2023シンポジウムの発表スライド案にてPDG部内での
リハ―サルを行い、修正した方が良い点を指摘して貰った。
・修正点:約3万件の特許群の特許分析の結果を説明するOne-Sheet図をもう1枚追加
して、説明時間を約3分にする。
・上記の3枚のOne-Sheet図の「特許の目的の説明語句のフォントを更に大きく変更する。」
・想定Q&Aを、PDG部会メンバーからして貰い、それに答える練習を実施した。
・発表をZOOMで行うための練習を6/26の17時からINFOPROシンポジウムの
事務局の設定で行った。
2.Japio-YEARBOOK2023の執筆原稿のチェック検討(全員)
・今年の執筆原稿では図としてOne-Sheet図が多く、しかも、1頁に収めるために、
Wordファイルが勝手に形崩れが起こるようになり、修正して貰った。
・PDG部会のメンバーから指摘があった修正点を加筆して、6/22夜に原稿をJapio-
YEARBOOK事務局に提出した。Wordファイルの形崩れの対策として、初校のPDF版
にて修正・加筆する方針に切り替えた。
3.来年のINFOPROシンポジウムに向けての、今年の研究テーマ案が出された。
SDGsに関連するテーマとして、「資源ロス(1)、食物ロス」と
「資源ロス(2)、代用食」の提案があり、資料として「秩父161号」と「秩父162号」が
提供された。7月のPDG部会から討議と検討を開始したい。
2023年05月
1.5月度の定例のPDG部会 (5/25)
・一般口頭発表の査読結果が届いた。そこで、修正案を作成し、PDGメンバーの
意見とアドバイスを頂いた。
・査読後に作成した修正原稿案を詳細にチェックして、WORDファイルにて
修正案を示して頂いたので、その詳細説明を受けた。
・更に、全員で自由討議を行い、その他に修正箇所の数か所を具体的にご教示を頂いた。
・担当は、直ぐに皆様のアドバイスを全面的に受け入れて修正し、翌日の5/26に
INFOSTA事務局に修正予稿集を提出した。
・INFOPROシンポジウムの発表者の有料登録を行った。4400円。
・三胴船特許のPCT出願の願番が正式に決まった。
・第4案の特許出願は、完全に断念し、公知化の方向に切り替えた。
2.PDG部会の2022年度の事業報告書を清田会長に提出した。
3.トピックス
・特になし。
2023年04月
1.4月度の定例のPDG部会 (4/20)
・一般口頭発表への申込は、3/23夜に完了した。この予稿集の原稿は、
4月10日に提出を完了した。ここまでは、PDG部会の前に完了。
・予稿集の原稿を2基の収納縦型ロープ巻き取り機で図6を作成した提出した。
全員で、特許出願が可能かできないか、議論した。(PDG部会)
・「4/3の特許出願案(第2案)では、発明観点が複数あり、特許出願の
要件に最適でない」と、判断意見が述べられた。
・対策として、「第1請求項を方法特許案にして、第2請求項を第1項の実施形態の船舶で
出願する修正案」が川島先生から示唆され、それに沿う形で、特許出願を検討する。(合意)
・PDG部会以降で、2基の収納縦型ロープ巻き取り機では、「机上空論であり実現不可である」
と指摘があり、PETボトルの2本で模型を作り実験してみて、
初めて「考え方が間違って居り、ご指摘の通り」と判明した。
・その後、第4案として1基の収納横型超広幅ロープ巻き取り機の構造にして、特許図面と
請求項1(方法特許)と請求項2(それを実現する船、物特許)の改定案で特許出願の
検討を開始した。(特許図面を先ず書く。請求項1と2を文章化。)
・明細書素案第4案を4/10までに作れなかったので、6/10までに明細書の完成は
難しくなりそうである。
2.トピックス
・特になし。
入会について
- 開催: 隔月
- 年会費: 5,000円
- コアパーソン: 桐山 勉
- 専門部会(SIG) : パテントドクメンテーション部会の活動(<特集>OUG/SIGの活動紹介)(情報の科学と技術)