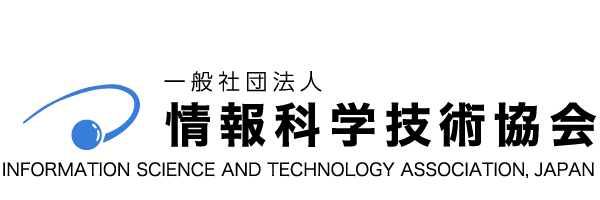ACADEMIC RESOURCE GUIDE(ARG)2025-04-14発行 ISSN 1881-381X
===================================
◆ レポート ◆ - Science, Internet, Computer and …
===================================
「情報の力で未来をデザインするーINFOSTA75周年と新たな挑戦」
清田陽司(一般社団法人 情報科学技術協会[INFOSTA]会長)
1950年に「UDC協会」として発足した一般社団法人 情報科学技術協会(INFOSTA)は、今年2025年に設立75周年を迎えました。この節目にあたり、私たちは「社会に貢献する情報専門家のコミュニティ構築」をテーマとした記念事業に取り組んでいます。その一環として、現在クラウドファンディングを実施しています。
・情報の力で社会を変える – INFOSTA75周年、新たな挑戦へ
本稿では、INFOSTAが75年間で培ってきた思想と実践を振り返るとともに、生成AIが急速に普及する中で、情報に向き合う人間の役割が再び問われている今、私たちが目指す「未来情報社会のデザイン」についてお伝えします。
■INFOSTAとは何かー設立の背景とこれまでの歩み
INFOSTAの歩みは、戦後日本が科学技術立国を目指していた時代の、ある切実な課題に端を発しています。
第二次世界大戦後、日本では急速に進む産業復興と科学研究の推進にあたって、国内外に散在する科学技術文献をどのように体系化し、利用可能な形で整備するかが大きな課題となっていました。当時の日本には、図書館資料や文献情報を国際水準で分類・共有するための制度や技術が決定的に不足しており、情報整理のための「共通の言語」とも言うべき仕組みが求められていたのです。
このような背景のもと、1950年、国際十進分類法(UDC; Universal Decimal Classification)の導入と普及を目的とする「UDC協会」が発足しました。これは、現在のINFOSTAの前身となる組織です。戦前から一部の学術機関や企業(東芝、三菱電機など)でUDCの活用が試みられていた流れを受けて、戦後の再建期においてその国際的な分類法を定着させるべく、産業界・学術界を巻き込んだ組織が誕生したのです。
初代会長には、東北大学教授の八木秀次氏(著名な八木・宇田アンテナの共同発明者)が就任。発足メンバーには、東京大学の井口昌平氏、国立国語研究所の柴田武氏、電気通信研究所の中村幸雄氏、日本印刷学会の山本隆太郎氏など、各分野を代表する専門家たちが名を連ねました。
当時の目標は、単なる分類法の導入にとどまらず、「文献情報の分類・検索能力を体系的に高め、科学技術情報の生産・管理・活用に資する基盤を築く」ことにありました。また、国際的な情報共有の枠組みに日本が参画・貢献することも重視され、1951年には日本学術会議の支援のもとで国際ドクメンテーション連盟(FID)への国家加盟を果たすなど、戦後復興期における国際連携の先駆けとしての役割も担っていました。
設立当初から、理論と実践の双方において積極的な活動が展開されました。1950年には会誌『UDC Information』を創刊し、理論的研究や活用事例の共有を開始。同年11月には第1回のUDC講習会を開催し、専門職の育成にも力を注ぎました。1955年にはUDC分類表の日本語簡略版(第1版)を刊行し、国内普及の基盤を整えました。
こうした基盤整備の成果を踏まえ、1958年には組織名称を「日本ドクメンテーション協会」と改め、対象領域を文書分類から図書館情報・科学技術文献の整理全般へと拡張。その後も情報技術の進歩と社会のニーズの変化に対応し、1986年には現在の「情報科学技術協会(INFOSTA)」へと名称を変更しました。この改組によって、オンライン情報検索やデータベース管理といった新たな領域をも活動範囲に含め、文字通り「情報科学と技術の架け橋」として再出発を果たしたのです。
現在、INFOSTAが取り組んでいる検索技術者検定や、AI利活用研究会、セミナー・研究会活動、学術誌『情報の科学と技術』の発行などは、こうした70年以上にわたる歴史と理念の積み重ねの延長線上にある実践です。
つまり、INFOSTAの歴史とは、「分類」から始まり「検索」へ、そして「活用」へと拡張してきた「情報のライフサイクル全体を見据えた支援コミュニティの歩み」ととらえることができます。設立当初の理想ー情報を正しく整理し、活用し、社会へ還元するという使命は、形を変えながらも今なお息づいています。
■デジタル社会における「情報専門家」の再定義
今、生成AIやSNSの浸透によって、「情報」の定義や扱い方そのものが大きく変わろうとしています。誰もが大量の情報にアクセスできる一方で、信頼性や文脈の欠如といった課題も顕在化しています。
このような時代だからこそ、人が介在することの意味と価値は、むしろ高まっていると考えています。私たちINFOSTAでは、「未来をデザインする存在」としての情報専門家像を再定義し、その実現を支えるコミュニティづくりに注力しています。
2022年11月に鳥取で開催された「都道府県立図書館サミット」では、「デジタル社会の行き着く先にライブラリアンが果たしうる役割を考える」というテーマで基調講演を行いました。
・「デジタル社会の行き着く先にライブラリアンが果たしうる役割を考える」
ここで私は、Code4Lib JAPANなどで培ってきた「コミュニティ・オブ・プラクティス」の考え方に触れ、未来を担う情報専門家のための学びと協働の場を構築する必要性を訴えました。
■会長として2年半、見えてきた課題と改革の方向性
INFOSTAの会長を拝命してから約2年半、私が痛感してきたのは、INFOSTAが長年にわたって築いてきた知見やネットワークがもつ「内在的な価値」と、社会から見たときにその価値がどう見えているかーこの“外とのギャップ”でした。
INFOSTAが取り組んできた、会誌の発行、検索技術者検定、各種セミナーや研究会、そしてISO・JIS原案作成を含む標準化活動などは、いずれも実務家が学びを深め、信頼できる情報を社会に還元するための貴重なインフラです。しかし、それらの意義が十分に伝わっていない場面も少なくありません。
かつて、こうした「コミュニティに属することの価値」は、言語化を必要とせず、懇親会や現場での会話、連帯感のなかで自然と共有されてきました。人が集い、共に働き、語り合う中で、知識と文化が受け継がれ、次の担い手が育ってきたのです。
しかし、私たちの世代ーいわゆる氷河期世代以降、社会の構造や職場の在り方は大きく変わりました。目標管理制度の普及、成果主義の浸透、デジタルコミュニケーションの定着などにより、「学び続ける仲間がいること」の意味や価値が、若い世代にとっては見えにくいものになってきています。
加えて、日本社会全体が本格的な人口減少局面に突入する中で、これまでと同じ規模・同じ形式でコミュニティを維持し続けることは、現実的に難しくなってきています。INFOSTAも例外ではありません。「続けることそのものが価値である」という前提を問い直し、「次の世代が受け取りたくなるかたちでコミュニティを再構築する」ことが不可欠だと考えています。
つまり私たちは今、「何を残し、何を手放すのか」を見極める、岐路に立っているのです。勇気をもって終わりにすべき活動もあるでしょう。それは決して否定ではなく、未来に向けた肯定的な選択です。「何も変えずに次の世代に受け渡すことが、最善の継承とは限らない」のです。
私は、かつての恩師・長尾真先生の姿を思い出します。電子図書館構想や用例ベース機械翻訳など、先駆的な研究を多く手がけられた先生は、生涯にわたり「次の世代のために道を拓く」という姿勢を貫かれました。自身の業績を誇ることなく、常に後に続く人たちのために、問いを残し、場を耕し、背中で導いてくださいました。
もちろん、私などはその足元にも及びませんが、INFOSTAの会長という重責をお預かりしている身として、その精神の一端でも受け継ぎ、「次の世代にとって本当に必要とされるコミュニティとは何か」を問い続けたいと考えています。
その想いのもと、INFOSTAでは現在、以下のような改革に取り組んでいます。
・AI利活用研究会の立ち上げなど、時代の課題に即した新たなコミュニティの創出
・Peatixの導入や検索技術者検定のCBT化など、業務のデジタルシフトと柔軟化
・タスクフォース(TF)型の意思決定体制への転換(リブランディングTF、コミュニティ形成TF、定款等改正TFの設置)
・事務体制の再編・スリム化(事務局のシェアオフィスへの移転)による持続可能な組織運営
・所期の目的を達成した委員会活動の整理(会誌経営委員会、広報委員会の活動休止)
・非会員や若手世代への接点拡大に向けた情報発信スタイルの刷新
これらの改革の根底にあるのは、「10年後、情報専門職が誇りと自信をもって集える場をどうしたら残せるか」という未来志向の問いです。イベントや会員数といった短期的な成果に留まらず、持続可能で意味あるコミュニティとして、次の世代に希望を託せる組織でありたい。
INFOSTAが今まさに目指しているのは、そのような変革です。
■唯一の正解のない時代に、自分なりの視座をもつということ
私は2021年から2022年にかけて、人工知能学会誌の編集長として、レクチャーシリーズ「AI哲学マップ」を企画しました。AIが急速に進化するなか、「人工知能とは何か」「情報とは何か」「人間とは何か」といった問いを、哲学の視点から捉え直す試みでした。この内容は2024年11月に『人工知能と哲学と四つの問い』(オーム社)として刊行されました。
・人工知能学会監修、三宅 陽一郎、清田陽司、大内孝子編『人工知能と哲学と四つの問い』(オーム社、2024年、3630円)
「哲学」という言葉には、どこか遠い世界の学問という印象を抱く方も多いかもしれません。しかし本来、哲学とは日常の中で私たち一人ひとりが直面する問題ー「なぜそれをするのか」「何が正しいのか」「どう生きるべきか」ーに正面から向き合う営みであり、自分なりの軸を育てていくための思考の技術でもあります。
たとえば、生成AIの爆発的な普及により、私たちは「人間と情報の関わり方」そのものを問い直す時代に入っています。AIが生成した文書や画像が日々行き交い、「これは本当に人間が作ったものなのか」と確認することさえ困難になりつつある今、図書館情報サービスのあり方や、情報専門家の役割も、これまでの延長線上では答えを出せない局面に差し掛かっています。
過去の成功体験や「周囲からの評価」に頼るだけでは、未来を切り拓くことはできません。目の前に広がる問いの多くには、唯一の正解がありません。だからこそ、「自分は何を大切にしたいのか」「どのような社会を望むのか」といった自分なりの視座を持ち、それに基づいて行動することが、かつてないほど重要になっています。
その視座は、独りで獲得できるものではありません。他者との対話のなかで、異なる視点に触れ、迷いながら問いを深めていくーそうしたプロセスこそが、視座を育てる営みであり、コミュニティに参加することの意義でもあると私は考えます。
75周年記念事業を通じて、私たちは、そうした「問いに向き合う仲間が集う場」をつくりたいと願っています。時代の変化に翻弄されるのではなく、そこに自分なりの問いと軸を持ち、他者とともに未来をデザインしていく。そんな営みを支えるコミュニティの在り方を、これからもINFOSTAという場から提案していきたいのです。
■75周年記念事業で目指すもの
今回の記念事業では、単なる過去の振り返りではなく、「未来に必要とされる情報コミュニティとは何か」を問い直す場にしたいと考えています。
具体的には、
・「未来のコミュニティ像」を語り合う記念イベントの開催
・科学情報・検索技術のアーカイブ化及び公開
・次世代の分科会・専門部会・ユーザー会の設立支援
などを通じて、情報専門家が主体的に情報社会の未来を形づくるための「新たな起点」を生み出したいと考えています。
記念イベントの第一弾として、INFOSTA前会長の山崎久道氏とのオンライン対談を開催いたします。
・INFOSTA 創立75周年記念イベント: INFOSTAの過去と未来(仮)
2025年4月30日(水)18:00~19:00
Zoom Webinar 参加無料
また、記念事業の一環として、クラウドファンディングを以下のサイトにて実施しております。
・情報の力で社会を変える ーINFOSTA75周年、新たな挑戦へ
2025年3月28日(金)~5月22日(木)17:00
もし趣旨にご賛同いただけるようでしたら、ご支援をいただけると幸いです。
■おわりにーともに未来を創る仲間へ
私たちは、「ともに学び、ともに育ち、ときに“遊びながら”気づきを得る」仲間がいることこそが、情報社会において最も価値ある資源だと信じています。INFOSTAという場が、そうした学びと遊びが交差する、明るく自由なコミュニティであり続けたいと願っています。
「情報を通じて社会に貢献したい」「信頼できる知識を次の世代に伝えたい」と願うすべての人に、INFOSTAは開かれた場でありたいと考えております。
皆さまにおかれましても、ぜひクラウドファンディングを通じて、私たちの取り組みにご関心を寄せていただければ幸いです。
未来の情報社会を、ともに“楽しく”、創っていきましょう。
[筆者の横顔]
清田陽司(きよた・ようじ)。不動産や介護分野など、業界にまたがる社会課題に取り組むAI研究者。1975年 福岡県生まれ。2004年 京都大学大学院情報学研究科 博士課程修了。東京大学情報基盤センターに助教として在籍中の2007年に株式会社リッテルを共同創業、国立国会図書館リサーチ・ナビなどの図書館情報ナビゲーションシステムの実装に取り組む。
2011年の株式会社LIFULLによる企業買収を経て不動産テック領域のAI研究開発に従事。2017年に株式会社メディンプルを創業、業界横断のAI社会実装に関わり、4社対等合併により2022年から株式会社FiveVai取締役。2024年、麗澤大学(千葉県柏市)に新設された工学部に教授として着任。
情報科学技術協会 会長(2022-)、人工知能学会 理事(2020-2022、2023-)、Code4Lib JAPAN共同代表(2011-)などを担当。博士(情報学)。 https://www.kiyota-yoji.net/
権利表示の指定
この記事は、CC BY-SA 4.0/表示-継承 4.0 国際で利用できます。
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja